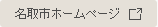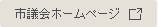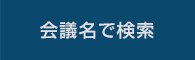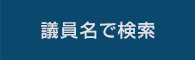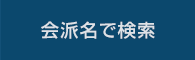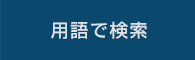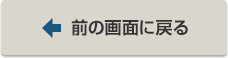※会議の録画映像をご覧いただけます。
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Im5hdG9yaS1jaXR5XzIwMTUxMjA3XzAwNDBfb25vZGVyYS1taWhvIiwicGxheWVyU2V0dGluZyI6eyJwb3N0ZXIiOiIvL25hdG9yaS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwL2ltYWdlL3RodW1ibmFpbC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL25hdG9yaS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1uYXRvcmktY2l0eV8yMDE1MTIwN18wMDQwX29ub2RlcmEtbWlobyZpc2xpdmU9ZmFsc2UiLCJjYXB0aW9uIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwidGh1bWJuYWlsIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwibWFya2VyIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInBhdGgiOiIifSwic3BlZWRjb250cm9sIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsIml0ZW0iOlsiMC41IiwiMSIsIjEuNSIsIjIiXX0sInNraXAiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwiaXRlbSI6WzEwXX0sInN0YXJ0b2Zmc2V0Ijp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInRpbWVjb2RlIjowfSwic2Vla2JhciI6InRydWUiLCJzZHNjcmVlbiI6InRydWUiLCJ2b2x1bWVtZW1vcnkiOmZhbHNlLCJwbGF5YmFja2ZhaWxzZXR0aW5nIjp7IlN0YWxsUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiRXJyb3JSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJQbGF5ZXJSZWxvYWRUaW1lIjozMDAwLCJTdGFsbE1heENvdW50IjozLCJFcnJvck1heENvdW50IjozfX0sImFuYWx5dGljc1NldHRpbmciOnsiY3VzdG9tVXNlcklkIjoibmF0b3JpLWNpdHkiLCJ2aWRlb0lkIjoibmF0b3JpLWNpdHlfdm9kXzQ3MSIsImN1c3RvbURhdGEiOnsiZW50cnkiOiJwdWJsaWMifX19
- 平成27年第5回定例会
- 12月7日 本会議 一般質問
- 日本共産党 小野寺 美穂 議員
1 子ども・子育て支援新制度について
(1)待機児童の定義の変更についてどう捉えているか。
(2)本来認可保育所の希望をしていて入所できない児童として定義すべきではないか。
(3)給付の対象となる施設・事業所がふえることにより、認定や給付の支給にかかわる市の事務量も増加しており、国の説明の遅れや準備期間も不十分だった。周知の徹底はどのように行われたのか。
(4)保育の必要量を市が認定するが、短時間区分とされた場合、延長保育料の徴収によって、標準時間区分より負担増となるのではないか。上限を標準時間保育料とすべき。
(5)新たに市町村の認可によって給付の対象となることができる小規模保育事業所は、3歳以降の保育が約束されていない。連携施設の確保についてどのように取り組んでいるのか。
(6)保育料の決定が、所得税額に応じた算定から市町村民税に応じた算定となった。そのことによって、負担増となっている実態はないか。
(7)親が育児休業中の場合、上の子の保育の取り扱いについて、実態は。
(8)保育行政における自治体の責任を果たせるよう、国に対して消費税によらない財源の確保と予算の大幅増額、最低基準や公定価格の改善、職員処遇の改善を求めていくべき。
2 貧困と格差の拡大について
(1)広がる貧困と格差についてどう捉えているか。
(2)本市の貧困率をどう捉えているか。
(3)子供の貧困も非常に深刻な状況になっている。市として市民生活を守る施策を展開すべきと考えるが、特に意を用いている点は何か。
(4)子供の学びを保障するために給付型奨学金制度を創設すべき。
3 被災者支援について
(1)閖上地区土地区画整理事業地外の被災者に対して住宅再建、土地の買い取り等を含めた対応をすべき。
(1)待機児童の定義の変更についてどう捉えているか。
(2)本来認可保育所の希望をしていて入所できない児童として定義すべきではないか。
(3)給付の対象となる施設・事業所がふえることにより、認定や給付の支給にかかわる市の事務量も増加しており、国の説明の遅れや準備期間も不十分だった。周知の徹底はどのように行われたのか。
(4)保育の必要量を市が認定するが、短時間区分とされた場合、延長保育料の徴収によって、標準時間区分より負担増となるのではないか。上限を標準時間保育料とすべき。
(5)新たに市町村の認可によって給付の対象となることができる小規模保育事業所は、3歳以降の保育が約束されていない。連携施設の確保についてどのように取り組んでいるのか。
(6)保育料の決定が、所得税額に応じた算定から市町村民税に応じた算定となった。そのことによって、負担増となっている実態はないか。
(7)親が育児休業中の場合、上の子の保育の取り扱いについて、実態は。
(8)保育行政における自治体の責任を果たせるよう、国に対して消費税によらない財源の確保と予算の大幅増額、最低基準や公定価格の改善、職員処遇の改善を求めていくべき。
2 貧困と格差の拡大について
(1)広がる貧困と格差についてどう捉えているか。
(2)本市の貧困率をどう捉えているか。
(3)子供の貧困も非常に深刻な状況になっている。市として市民生活を守る施策を展開すべきと考えるが、特に意を用いている点は何か。
(4)子供の学びを保障するために給付型奨学金制度を創設すべき。
3 被災者支援について
(1)閖上地区土地区画整理事業地外の被災者に対して住宅再建、土地の買い取り等を含めた対応をすべき。