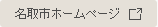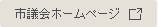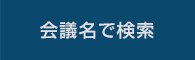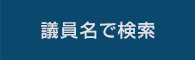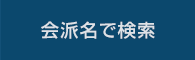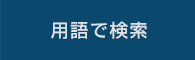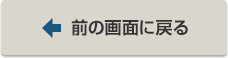※会議の録画映像をご覧いただけます。
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6Im5hdG9yaS1jaXR5XzIwMjUwNjEwXzAwMjBfdGVyYXNoaW1hLW1hc2FrbyIsInBsYXllclNldHRpbmciOnsicG9zdGVyIjoiLy9uYXRvcmktY2l0eS5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC9pbWFnZS90aHVtYm5haWwuanBnIiwic291cmNlIjoiLy9uYXRvcmktY2l0eS5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC8/dHBsPWNvbnRlbnRzb3VyY2UmdGl0bGU9bmF0b3JpLWNpdHlfMjAyNTA2MTBfMDAyMF90ZXJhc2hpbWEtbWFzYWtvJmlzbGl2ZT1mYWxzZSIsImNhcHRpb24iOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJ0aHVtYm5haWwiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJtYXJrZXIiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwicGF0aCI6IiJ9LCJzcGVlZGNvbnRyb2wiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwiaXRlbSI6WyIwLjUiLCIxIiwiMS41IiwiMiJdfSwic2tpcCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJpdGVtIjpbMTBdfSwic3RhcnRvZmZzZXQiOnsiZW5hYmxlZCI6ImZhbHNlIiwidGltZWNvZGUiOjB9LCJzZWVrYmFyIjoidHJ1ZSIsInNkc2NyZWVuIjoidHJ1ZSIsInZvbHVtZW1lbW9yeSI6ZmFsc2UsInBsYXliYWNrZmFpbHNldHRpbmciOnsiU3RhbGxSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJFcnJvclJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIlBsYXllclJlbG9hZFRpbWUiOjMwMDAsIlN0YWxsTWF4Q291bnQiOjMsIkVycm9yTWF4Q291bnQiOjN9fSwiYW5hbHl0aWNzU2V0dGluZyI6eyJjdXN0b21Vc2VySWQiOiJuYXRvcmktY2l0eSIsInZpZGVvSWQiOiJuYXRvcmktY2l0eV92b2RfMTI2OSIsImN1c3RvbURhdGEiOnsiZW50cnkiOiJwdWJsaWMifX19
- 令和7年第3回定例会
- 6月10日 本会議 一般質問
- 青雲倶楽部 寺嶋 雅子 議員
1 中学生海外派遣事業について
(1)令和6年度に実施したカナダ派遣事業の成果と課題について伺う。
(2)現在1・2学年を対象としているが、2学年のみの1学年制に戻すべき。
(3)派遣経験者が国際交流活動を継続するための情報提供及び情報発信機会の提供をどのように行っているのか伺う。また、ホームステイ受入れ家庭の増加策についても伺う。
(4)抽選に漏れた参加希望者や市民に向けて、広く派遣事業の報告を行い、国際化に対応した人材を育成すべき。
(5)派遣経験者が本市での国際交流活動に継続的に関わる仕組みを構築すべき。
2 国際交流及び多文化共生の体制づくりについて
(1)市内外国人居住者数や国籍、家族構成等の傾向の変化と、本市の国際交流及び多文化共生に関する課題をどう捉えているのか伺う。
(2)国際交流及び多文化共生の取組は外国人の支援にとどまらず、地域全体に恩恵をもたらすものであるという視点から、国際交流協会設立に向けて市としてどのように取り組むのか伺う。
(3)任意団体として活動している市内の国際交流団体が、委託事業以外にも提案事業や相談対応など大きな役割を果たしていることを評価し、法人格取得に向けた支援を行うべき。
(4)同団体の国際交流事業について、活動全般に対する運営費を助成すべき。
(5)令和5年度に実施した外国人居住者ニーズ調査結果の活用について考えを伺う。
(6)外国人が働く企業や施設経営者を把握し、外国人の生活支援について市、企業等と国際交流団体が意見交換をする機会を設けるべき。
(7)防災や環境、学校教育等においても多文化共生の課題は今後増加するものと考えられる。多文化共生に関する行政内部の体制として、庁内に専門の係を設置すべき。
(1)令和6年度に実施したカナダ派遣事業の成果と課題について伺う。
(2)現在1・2学年を対象としているが、2学年のみの1学年制に戻すべき。
(3)派遣経験者が国際交流活動を継続するための情報提供及び情報発信機会の提供をどのように行っているのか伺う。また、ホームステイ受入れ家庭の増加策についても伺う。
(4)抽選に漏れた参加希望者や市民に向けて、広く派遣事業の報告を行い、国際化に対応した人材を育成すべき。
(5)派遣経験者が本市での国際交流活動に継続的に関わる仕組みを構築すべき。
2 国際交流及び多文化共生の体制づくりについて
(1)市内外国人居住者数や国籍、家族構成等の傾向の変化と、本市の国際交流及び多文化共生に関する課題をどう捉えているのか伺う。
(2)国際交流及び多文化共生の取組は外国人の支援にとどまらず、地域全体に恩恵をもたらすものであるという視点から、国際交流協会設立に向けて市としてどのように取り組むのか伺う。
(3)任意団体として活動している市内の国際交流団体が、委託事業以外にも提案事業や相談対応など大きな役割を果たしていることを評価し、法人格取得に向けた支援を行うべき。
(4)同団体の国際交流事業について、活動全般に対する運営費を助成すべき。
(5)令和5年度に実施した外国人居住者ニーズ調査結果の活用について考えを伺う。
(6)外国人が働く企業や施設経営者を把握し、外国人の生活支援について市、企業等と国際交流団体が意見交換をする機会を設けるべき。
(7)防災や環境、学校教育等においても多文化共生の課題は今後増加するものと考えられる。多文化共生に関する行政内部の体制として、庁内に専門の係を設置すべき。